「1319」 副島先生の新刊本2冊。『ロスチャイルド200年の栄光と挫折』(日本文芸社)と石平(せきへい)氏とのケンカ対談『中国 崩壊か 繁栄か!? 殴り合い激論』(李白社)が発刊されました。世界の実像を知るのにおすすめの2冊です。 2012年7月19日
- HOME
- 「今日のぼやき」広報ページ目次
- 「1319」 副島先生の新刊本2冊。『ロスチャイルド200年の栄光と挫折』(日本文芸社)と石平(せきへい)氏とのケンカ対談『中国 崩壊か 繁栄か!? 殴り合い激論』(李白社)が発刊されました。世界の実像を知るのにおすすめの2冊です。 2012年7月19日
副島隆彦を囲む会の中田安彦です。 本日は2012年7月19日です。
世界の金融の歴史を知り、現在、超大国の中国の未来を予測する上で非常に有益な本が発刊されました。一冊は副島隆彦の単著、もう一冊は元中国人評論家で人気の石平(せきへい)氏との対談です。
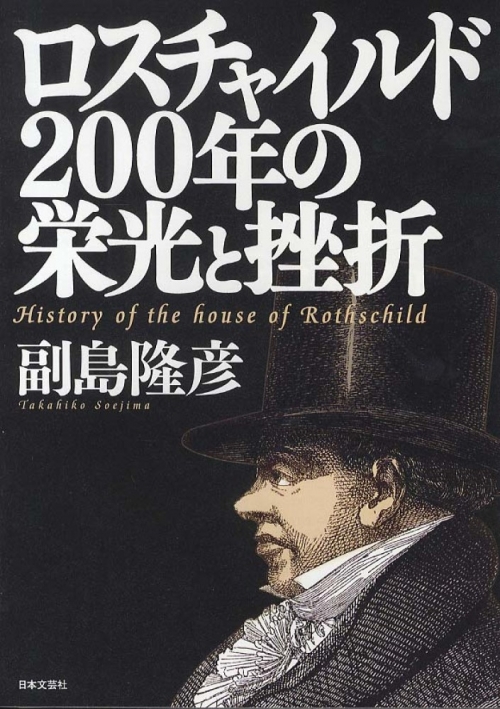

一冊目は『ロスチャイルド 200年の栄光と挫折』(日本文芸社)という本で、現在から過去に至るまでの欧州の金融ファミリー、ロスチャイルド家の歴史と活動と成功と失敗を、ふんだんにイラストと写真を使って描いています。
ロスチャイルド関連の本は近年、いろいろなものが出版されました。ただ、日本では根拠がない「陰謀論」(都市伝説と同じ意味)と結び付けられて、あまりに伝説化、肥大化したロスチャイルド像が広まっていたこともあり、ここでその辺の情報を一気に整理した本が出たのは意味があることだと思います。
本書はこれまで日本で出ている、ロスチャイルド研究本、広瀬隆、横山三四郎(よこやまさんしろう)、デリク・ウィルソン、フレデリック・モートンらの翻訳書を踏まえつつ、学問道場で紹介された最新情報も踏まえながら、等身大のロスチャイルド家とは何かを描き出そうとしています。
二冊目の『中国 崩壊か 繁栄か!? 殴り合い激論』(李白社)は、中国人だったが現在は日本人に帰化した、大人気の中国問題の評論家の石平氏と副島先生のケンカ対談です。武田邦彦氏とのケンカ対談で去年、原子力業界の裏側の話を巧みに引き出した副島隆彦のケンカ対談技術(アタックソナーによる情報引き出し術)が今回の本でも発揮されています。
私は、この対談は絶対に実現しないだろうと思っていたのですが、実現してみると、互いに主張を述べ合いつつも、最後はアジア人どうしで大きな理解ができているようでもあり、なかなか不思議なものだと思ったものです。
現在の中国の政治事情、経済事情、尖閣諸島問題などについても話し合っている。このケンカ対談、どちらに分があるかは是非、お読みになってお確かめください。
なお、このケンカ対談には、CDによる音声ヴァージョンもあります。すでにこのコーナーでも一度ご紹介しましたが、再度ご紹介します。
ただ、このCDセットは版元の李白社さまのサイトでのみの取り扱いです。本サイトからはお申込みはできませんのでご了承ください。
◯CDのお申込み⇒http://www.rihakusha.co.jp/cd-dvd/seki_soe_cd_r.html
二冊の本に関しては、先に発刊された植草一秀先生との対談本『国家はこうして『有罪(えんざい)』をつくる』(祥伝社)とあわせてこのサイトで取り扱っております。
また、月末27日ころにはPHP研究所から『隠された歴史 そもそも仏教とは何ものか?』という歴史本も出る予定です。
4冊セットでお求め頂く場合はこちらの本の販売日も確認した上で、当サイトからお申込みいただくこともできます。(歴史本については入荷次第このサイトでもお知らせします)
◯書籍のお申し込みはこちらです⇒https://www.snsi.jp/shops/index#book
それでは以下に『ロスチャイルド 200年の栄光と挫折』と『中国 崩壊か 繁栄か!? 殴り合い激論』のまえがきとあとがきを掲載します。
===
『ロスチャイルド 200年の栄光と挫折』(日本文芸社)
はじめに
私たち日本人は、ロスチャイルドのことを知りたがっている。それなのに、手頃な解説本がない。
だから、この本が、欧州ロスチャイルド家200年の全体像を大づかみで理解できることを真剣に目指した。日本では、それなりの読書人を自負する人であっても、この華麗なるユダヤ系の巨大金融財閥の全体図を把握できていない。
たとえばロンドン家2代目当主のライオネルと4代目ウォルター、パリフランス家2代目アルフォンスと4代目ギーが行なったこと(重要な歴史事件にどのように関わったか)を区別することができない。そのために愚かなる×陰謀論なるものが、今も日本国内にはびこっている。この本は、この困難な課題にも正面から挑戦した本である。
ただし、世界権力者たちによる権力者共同謀議(けんりょくしゃきょうどうぼうぎ)は有る。歴然として存在する。確かに19世紀(100年前)の世界はロスチャイルド財閥が操る大英帝国の時代だった。彼らが数々の悪事も実行した。
だが20世紀になってからのこの100年余は、アメリカ・ロックフェラー財閥が世界を支配した。ロックフェラー石油財閥が欧州ロスチャイルド財閥に取って替わり、コンスピラシー(権力者共同謀議)の巨悪を実行して来た。
いつの時代も、世界で一番大きな資金を持つ集団がその時々の世界をいいように動かす。この観点をおろそかにしてはいけない。 この本は、ロスチャイルド家の創業以来の220年間の全体像に明確な輪郭を与える。欧州ロスチャイルド財閥220年の中の主要な人物たち26人を相互に関連づけながら解説する。わかりやすいように、本文と家系図に、主要な人物たち26人の通し番号を付けた。巻頭に折り込んだ家系図もじっくりと何度も見てほしい。
この本が編まれた動機は、ゆえに、×「ロスチャイルド家による世界支配の陰謀」をバラまき続ける低能たちを粉砕することである。
世界を操る「闇の勢力」など存在しない。世界支配主義者たちは堂々と表に出てきて、公式・非公式の会議を開き、公然と世界を支配している。巨大な金の力で、各国の高官・公職に就く人間たちを、人事面から左右して各国の政治に強い影響を与えている。
「ヨーロッパ・ロスチャイルド家が米ロックフェラー家を背後から操っている」と主張する裏のある者たちを、この本で最終的に撃滅する。そのための正確な知識の本としてこの本は世に出る。この本の著者である私は、×陰謀論という不正確で不適切なコトバの蔓延を拒否し訂正させ、やがて消滅させる覚悟である。
「コンスピラシー」とは○共同謀議(きょうどうぼうぎ)のことである。従って欧米で使われるコンスピラシー・セオリー conspiracy theory は、正しく「権力者共同謀議(はある)理論」と訳さなければならない。
この本の影響で、今後、日本から少しずつ×陰謀論というコトバが消えてゆく。×陰謀論は廃語 absolete wordとなってゆく。そしてそれに代わって、コンスピラシーは、権力者共同謀議と正しく呼ばれるようになるだろう。そして、権力者共同謀議は存在するのだと主張する理論をコンスピラシー・セオリー conspiracy theory といい、それを主張する者たちをコンスピラシー・セオリスト conspiracy theorists という。この「権力者共同謀議理論」が正しく日本国内で認められるようになってほしい。
その日まで私は、世界各国にいる同志たちである真実言論派 truth activists の一人として、日本を自分の持ち場として闘い続ける。私は事実と真実以外の何ものも恐れない。それが政治知識人、思想家であることの堅い決意である。
2012年6月
副島隆彦
おわりに
私の歴史観は、「世界で一番大きなお金(資金力)を持つ者が、その時の世界を支配する」というものである。巨大なお金の動き(利益のための活動)の話を抜きにして、文献証拠にだけ頼る歴史学をいくらやっても本当の歴史はわからない。
歴史学を専攻する大学教授たちのほとんどは貧乏な学者だ。企業経営も知らず、泥くさい生の政治も知らない学者たちに本当の歴史は描けない。だから歴史を見る場合に、「大きなお金の動きの真実」を観察する目を持つべきだ。人類史を冷静に見るなら、あくまで、その時代、時代の権力闘争(パワーストラグル)と巨大資本の動きに着眼すべきである。
大戦争(大会戦)があって両軍各々5万人、計10万人の兵(軍団)がぶつかった、と歴史家は自分の目で見てきたようなウソを書く。しかし本当は、その時の300人、500人しか決死の突撃をしない。残りの9割は、自分が死なないで済むことばかり考えている。1万人、2万人の兵隊を動かすのに、いったい、毎日毎日、どれほどの資金が必要か、をこそ考えるべきなのである。
たとえば、300人の従業員を抱える中堅企業の社長(経営者)がどれほどの苦労をして社員の給料(賃金)を払っているか。このことから常に世の中を見るべきなのである。大事件、戦争の背後にある「お金の動き」を知らずに歴史を語ると「子供の知識」になってしまう。
私は、「はじめに」でも書いたとおり、コンスピラシーは、「権力者共同謀議」と訳すべきだと考える。共同謀議とは、あくまでその国の権力者(支配者)たち自身による共同謀議でなければならない。その国の警察によって一網打尽にされてしまうような小さな企み、謀ではない。一番大きな資金を握っている本当の支配者たちが、主要な公職の人事権を実質的に握り、政治を背後から(非公式の力で)動かす。だから、私は、コンスピラシー conspiracyのことを「権力者共同謀議」と訳すべきだと主張してきた。
そしてこの権力者共同謀議はあると主張するコンスピラシー・セオリストを、「権力者共同謀議はある論者」と訳すしかない。
私は×「陰謀論者」というコトバが大嫌いである。それを受け入れ自認する者たちだけが使えばいい。どうせ生来の頭のおかしな人間たちである。この私まで、陰謀論者だとレイベリング(レッテル貼り)することで、私の日本国での真実暴きの言論活動の影響力をそぎ落とそうとする者たちがいる。謀略人間たちだ。私はこの者たちと闘い続ける。
大英帝国のピークは、1901年のヴィクトリア女王の葬儀の時である。そしてこのあと1914年に世界覇権は、ヨーロッパからアメリカに移った。その論証は本書の中で行なった。1914年からは、石油の力(エネルギー革命)で成り上がったアメリカの新興財閥であるロックフェラー家が世界を支配し始めたのである。ヨーロッパとロスチャイルド家はこの時から衰退を始めた。ロックフェラー家が世界で一番大きな力を握った。そして、アメリカ国内だけでなく、主要な国際機関の公職者たちの人事権(任命権)までを握り、世界政治を自分たちの思うように動かし続けた。これが大きな事実である。
だから今の今でも、彼らアメリカ・ユダヤ帝国の属国(従属国)の一つである、私たち日本国の財務大臣や金融担当大臣の実質的な任命(権)はアメリカが握っている。そうではないのか。財務と金融の大臣に署名をさせることで、5兆円でも10兆円でも、アメリカ国債を買わせる(円高“阻止”介入と称して)ことができる。アメリカの日本国への支配と干渉はこのように今も本当にヒドいものである。
だがそれもあと何年かで終わる。アメリカ帝国(=ロックフェラー石油ドル体制)は衰退が著しいから、もうすぐ倒れる。
人類史は次々と興る帝国(覇権国)の興亡の歴史である。帝国は周辺の数十カ国を家来の国として束ねて支配する。ひとつの帝国(王朝)の長さは、だいたい4世代(30年かける)である。だからだいたい世界覇権は120年間と決まっている。この120年の周期で世界覇権(支配権)は移ってゆく。私はこのように世界史を冷酷に概観する。過去の諸事実から冷静に組み立てられる理解を近代学問(サイエンス)という。
1859年に、アメリカの五大湖のほとりで石油の掘削に成功した。そこは今もオイル・シティという観光地になっているので、この石油と共に勃興したロックフェラー財閥が、早くも1880年代には、世界で一番大きなお金を握った。だからこの時から、世界支配は“金”と共に栄えたロスチャイルド家から、ロックフェラー家に移っていった。そしてこのあと世界覇権は、次の支配者、即ちスバリ中国へと移ってゆく。
その前の19世紀の1805年からの120年間が、ロスチャイルド家が世界を支配した時代だった。その前の100年間はフランス王国(ブルボン王朝)が覇権者である。そしてナポレオンが文字どおり、ヨーロッパ皇帝となった。ロスチャイルド家の創業者マイヤー・アムシェルと息子NM(ネイサン・マイヤー・ロスチャイルド。ロンドン家初代当主)はナポレオンを打ち倒すために文字どおり命懸けの闘いをやったのである(本書56~57ページ)。公式(正式)には、1931年に「金ポンド(兌換)体制」が終わった時に、大英帝国とロスチャイルド家の支配も終わったのである。
それなのに、今でもまだ「ロスチャイルド家が世界を支配している」と書く者たちがいる。それはロックフェラーに秘かに雇われた手先たちだ。
ロスチャイルド家について主要な文献は、以下の6冊である。
①横山三四郎著『ロスチャイルド家 ユダヤ国際財閥の興亡』(講談社現代新書 1995年刊)。②広瀬隆著『赤い楯 ロスチャイルドの謎』(上下巻 集英社 1991年刊。現在は集英社文庫 全4巻)。③フレデリック・モートン著『ロスチャイルド王国』(邦訳・高原富保 新潮選書 1975年刊)。④デリク・ウィルソン『ロスチャイルド 富と権力の物語』(上下巻 邦訳・本橋たまき 新潮文庫 1995年刊)。
それとこの一族の主要な人物である、⑤エドマンド・デ・ロスチャイルド著『ロスチャイルド自伝 実り豊かな人生』(邦訳・古川修 中央公論新社 1999年刊)。⑥フランス(パリ)家4代当主であるギー・ド・ロスチャイルド自身が書いた『ロスチャイルド自伝』(邦訳・酒井傳六 新潮社 1990年刊)の6冊である。
横山三四郎・戸板女子短大元教授の『ロスチャイルド家 ユダヤ国際財閥の興亡』と、『赤い楯』を書いた広瀬隆の二人はおそらく米ロックフェラー財閥の息のかかった者たちである。ロックフェラー家は、イギリスのロスチャイルド家が大嫌いで憎んでいる。恐れてもいる。かつて(1913年まで)自分たちがイギリス人に資金を借りて従属していたからである。今でもアメリカ人の支配階級はどんなに家柄を誇ってもイギリス貴族に頭が上がらない。
ロスチャイルド家は、どうやらイギリス王室から貴族(男爵)の称号をもらったのではない。ウィーンのハプスブルク家(ヨーロッパ皇帝の家系)から、貴族の称号をもらったのだ。及び財力と政略結婚の力で手に入れた。叙位権(じょいけん)は帝権(国王ではなく皇帝の権限)に属する。 ヨーロッパ貴族の称号は、アメリカ人の支配階級の者たちであっても絶対にもらってはいけない。なぜなら、アメリカ合衆国は、共和国であって、王国や貴族は存在してはいけないからだ(ただし、外国人や旅行者としてヨーロッパ貴族が訪問するのはかまわない)。だからアメリカ合衆国にはアメリカ国民であるなら、たとえサー(準男爵、バロネット)でもいてはいけない。
案外、この事実を日本人は知らない。平民であるロックフェラー家はロスチャイルド家が嫌いなのである。だから、「ロスチャイルド家についての研究」を、世界各国から学者、ジャーナリストたちを選抜して、特殊な留学や奨学金を与えてやらせる。
たとえば、ロン・チャーナウ著『タイタン ロックフェラー帝国を創った男』(邦訳・井上広美 日経BP社 2000年刊)という分厚い本がある。このおかしな本は、ロックフェラー1世を書いた伝記だが、ロックフェラーを賛美するばかりで、本当の穢(きたな)い泥臭い話は全く書かれていない。
ロックフェラー家につながる者たちが、推し進めている計画は、「ロックフェラー家はユダヤ系ではない」という打ち消しプロバガンダと、もう一つは、「だからロスチャイルド家を暴きたてるように調査、研究せよ」ということである。そうやって前記の書が日本でもできたのだ。
私たちは、この二書からもしっかりと学べばいいのである。その内容の客観事実である部分は公共財産であるから、どんどん利用していいはずだ。
その上で私が、更なる真偽判断を行なって「そうではない。真実はこうだろう」という物語の作り変えを本書でやった。私の書いたことにウソがあるというのなら、そのように主張してください。必ず反論します。
最後に。この本ができるのに、再び日本文芸社の水波康編集長と、グラマラス・ヒッピーズの山根裕之氏に大変お世話になった。記して感謝します。
2012年6月
副島隆彦
『中国 崩壊か 繁栄か!? 殴り合い激論』(李白社)
はじめに
「好敵手」との真剣勝負の激論で、思考を深化させた
石 平
このたび、副島隆彦氏との長時間の対談が実現できた。副島氏の言論活動は、もちろん以前から知っている。独自の視点から「怪奇複雑」な国際問題(とくに金融問題)に深く斬り込み、余人の追随できない近未来予測を行なう稀有の鬼才だ、という認識である。そして氏は中国問題に関しては、言論人の端くれの私とはまったく正反対の論陣を張っていることもよく知っている。
だが、よりにもよって、まさにこの「中国問題」をテーマにして、副島氏と私が対談することになったのだ。実は対談が決まった時点から、私自身も、それがかなりの激しい論争となるのではないかと予測して、いわば「刺し違える覚悟」を固めてきたわけである。
確かに、中国の政治経済問題に関して、とくに中国は今後どうなるかという近未来予測の大問題に関して、私と副島氏との間では大きな意見の相違があり、対談の中でも時々、互いに真剣を抜いての正面激突があった。今まで、多くの論客の方々と対談してきた私だが、これほどの激しい論戦を経験したのも初めてのことである。
しかしその一方、実に意外なことでもあるが、私と副島氏は多くの問題に関して、意見がまったく一致する点も多くあり、互いに意気投合してしまうような場面も時々見られた。話を進めているうちに、意見の対立する「好敵手」との真剣勝負を楽しむような雰囲気さえ、私たちの間に生まれてきたのである。
よく考えてみれば、それはまた、対談(あるいは対論)というものの持つ、本来ならの醍醐味の一つであろう。今まで体験してきた、意見の一致する人との対談は別の意味では大変有意義ではあったが、意見の異なる人との対談はまた、問題をより深く掘り下げて、思考を深化させるうえでは実りの多いものである。少なくとも私のほうは、副島氏との対談から多くのものを学び、自分自身の問題意識を深めることができた、という思いである。
しかも、中国の抱える諸問題に関して、とくに中国はこれからどうなるかに関して、私たち各自の持論を超えたところの示唆に富む、多くの論点(あるいは結論)がこの対談から引き出されているのではないかと思う。つまり知的生産の新しい成果は確実に、私たちの激しい対論(あるいは愉快なる対話)から生まれているのである。それはいったいどういうものであるかに関しては、読者諸氏の読んでの楽しみにとっておくが、ここでは、対談が終わってからの私の副島氏に対する認識の一つを記しておこう。
*
彼は実に、自分の主張あるいは論に対して、どこまでも誠実な人である。誰にも媚びることなく、誰をも恐れることなく、時流に流されるようなこともなく、堂々たる論陣を張るのは副島氏の一貫した流儀であることはよく知られている。が、彼との対談の中で私自身がしみじみと感じたのは、彼の論にはいっさいの虚飾と無用な遠慮のないことである。彼は心底から信じていることを論として語り、自分の論というものに全身全霊を懸けている。世の中の「論者」と称される人の中には、その人の論説とその人の人格はまったく別々であるケースが多い。だが、副島氏の場合、言葉と人格が渾然一体(こんぜんいったい)となって、副島の論はすなわち副島その人なのである。そういう意味では、彼は論者としては大変尊敬すべき人である。
もちろんその一方、副島氏の「遠慮のない論説」は時々、人を傷つけるようなこともあるのであろう。たとえばこの対談の中でも彼は時々、日本の保守的文化人を激しく批判するような発言を行なっているのはその一例である。もちろん私はこのような批判にはまったく同意できない。私はむしろ、氏によって批判される人々のことを大変尊敬している。
しかしそういうことは別として、副島氏との今回の対談は自分にとって、多くのことを学び、問題意識と思考を深める大変貴重な機会となったと思う。そして、副島氏と私が正面からぶつかりながら、問題を深く掘り下げていったこの対談本はきっと、皆様の中国理解を深める一助になることと信じている。
最後に、長時間にわたって対談してくださった副島隆彦氏と、この超面白い企画を提案し実行してくださった李白社の岩崎旭社長に、心からの御礼を申し上げたい。そして、本書を手に取ってくださる読者の皆様にはただただ、頭を下げて感謝したい気持ちである。
平成二四(二〇一二)年五月吉日
石 平
おわりに
〝アジア人どうし、戦わず〟の「大アジア主義」の立場で
副島隆彦
偉大な亡命知識人の伝統に連なる人
石平氏はこれからの日本国にとって大切な人である。それは彼が中国から日本への政治亡命者あるいは亡命知識人の伝統に連なる人だからだ。中国からの亡命知識人こそは二〇〇〇年にわたるわが国の宝物である。蘭渓道隆(らんけいどうりゅう、一二一三~七八。鎌倉時代中期に南宋から渡来した禅僧)や兀庵普寧(ごったんふねい、一一九七~一二七六。鎌倉時代中期に南宋から渡来した臨済宗の僧)らが元(モンゴル)の襲来を避けて亡命して来て、日本側に逸早く世界情勢を伝え、京都や鎌倉の五山文学を創始したのである。
それから四〇〇年後の江戸初期に、わが国一六番目の最後の宗派・黄檗宗(おうばくしゅう)の開祖・隠元禅師(いんげんぜんし、一五九二~一六七三。中国明末~清初期の禅宗の僧、日本黄檗宗の祖)が満州族(女真(じょしん)、のちの清朝)の侵略を避けるために来日した。
そしてもう一人、朱舜水(しゅしゅんすい、一六〇〇~八二。江戸時代初期に来日した、明の儒学者)が来た。彼は徳川氏(江戸幕府)に対して日本から明国へ援軍を求めてついに容れられず、日本に留まった。そして、日本の権力者たちは彼ら亡命知識人を最上級の扱いで丁重に迎えた。
わが国は二〇〇〇年来、中国文明 = 東アジア文明 の周辺文化国の一つである。
私は石平氏から中国五〇〇〇年の浩瀚(こうかん)なる知識と思想を熱心に習おうと思う(教えを乞おう)。漢文・漢籍教養こそは日本知識人の能力証明であった。漢籍教養のない者は、日本では知識人として認められない。漢字は日本人には外国からの文字である。この伝統は明治期に消えた。このあとは西欧とアメリカの思想と文物が席捲(せっけん)した。今の日本知識人に、漢文学者の伝統が途絶えたので、掛け軸の漢詩文を読もうとしてもまったく歯が立たない。渡来した中国知識人に、教えを乞うべく這いつくばったこの日本知識人の長い伝統に、私は連なる。
「折たく柴の記(おりたくしばのき)」の新井白石や、「寸鉄録(すんてつろく)」の藤原惺窩(ふじわらせいか)の深刻な悩みを私も共有する。山鹿素行(やまがそごう)や熊沢蕃山(くまざわばんざん)、山崎闇斎(やまざきあんさい)らのように、苦し紛れに、「本朝(わが日本国)こそは、中朝(中華、世界の中心)でごさる」と、逆転の発想で逃げ切ろうとした日本中華思想の系譜に私は安易には乗らない。
実はこの対談の初めで、石平氏は、宋・南宋の王朝(帝国、ファングオ)の制度と気風が、今の日本人の精神をつくっていると喝破された。驚くべき巨大な真実である。われわれ日本人は南宋期の中国人の精神を引き継いで保存しているらしい。ただ単に、禅宗仏教や雪舟(せっしゅう)派の水墨画や、〝竹林の七賢〟の風流に留まらない。私たち日本人とは、何と今に至るも、南宋期(一〇世紀から一三世紀)の中国人そのものだと石平氏は言う。その極限の美意識を体現する国民であるらしい。
願わくば、石平氏がこれ以上、〝中国崩壊論〟を日本国内で説いて回りませんように。なぜなら中国は崩壊しない。それどころか、これからますます隆盛(りゅうせい)して「和平崛起(わへいくっき)の大国」として世界を席捲する。「平和な世界帝国」になっていく運命にある。この大きな人類史上の動きを誰も押し止めることはできない。
民主政治(デモクラシー)こそは、中国人民の悲願
大和(だいわ、大きな平和。グランド・ピース〈grand peace〉。「やまと」ではありません。誰かが奈良時代にこの「大和」を、日本に泥棒して持って来た)こそは、歴代中華帝国(歴代の中国王朝)の理想であった。北京の天安門をくぐると、そこに巨大な太和殿(だいわでん)が現れる。これを観光客として見た日本人は多い。その先が紫禁城(皇帝の居所)である。
日本国天皇と武家将軍たちは明らかに、歴代中華帝国の「日王」(にちおう)であって、それが歴史の真実である。
人類史は世界のそれぞれの地域(region)で動乱と戦乱を繰り返した。中国人だけが虐殺民族なのではない。日本史にだって多くの政治的虐殺があった。
私は、石平氏が中国共産党の一党独裁を激しく怒り、その終焉(しゅうえん)を主張することに共感する。民主政治(デモクラシー、それは複数政党制と普通選挙制のことだ)こそは、中国人民の悲願である。私もこの方向には強く賛同する。
しかし、石平氏が、「反中国」にまで突き進まないことを希望する。自分が生まれ育った中国の大地と同族の人々を深く愛する、宋朝の士大夫(したいふ)の知識人の伝統にそろそろ立ち戻っていただきたい。私も士大夫(したいふ)である自覚を持って生まれた日本人だ。
石平氏が日本の中国大嫌い人間である右翼言論人たち(中国では日本(リーベン)右傾文人(うけいぶんじん)と呼ばれる)の支援を受けて、中国人(チャンコウロン)を警戒し、中国が大嫌いである経営者たちのネットワークで大切にされる理由がわからぬではない。それが亡命知識人なるものの運命だからだ。私は啞然として、この様子をずっと眺めてきた。このたび、石平氏と親しく対話する機会を得て、欣喜雀躍(きんきじゃくやく)としている。
偏った考えの彼ら日本右翼言論人(右傾文人)たちは、やがて少しずつ消えていく。彼らはなぜかアメリカ帝国にだけは異様に這いつくばる人々である。
この点を私が眼前で指摘すると、彼らは途端に横を向く。
私はアメリカの買弁(ばいべん)を平気でやる偽物ではない。本物の日本右翼(本物の愛国者)の伝統である「大(おお)アジア主義」の立場に連なる。だから、「アジア人どうし、戦わず」(騙されてやらされる再びの戦争への道だけは何としても阻止しなければならない)の旗を掲げ続ける。石平氏にも、こういう知識人勢力が日本に現存することを何とかご理解いただきたい。
日本は、アメリカ帝国と中国帝国の二つの帝国(超大国)の狭間で、両方からの強い圧迫に耐えて、できる限りの独立自尊(どくりつじそん、福澤諭吉先生が言った)の道を模索し、繁栄していく国であるべきだ。アメリカ帝国のほうは急速に衰退を早めており、東アジアからもやがて撤退していくだろう。
日中の真の架け橋の文人(ぶんじん)となることを期待する
私が、東京大学出のエリート日本官僚(たかが上級公務員たち)を鼻で嗤(わら)うのと同じで、石平氏も、北京大学出で中国政府官僚となり駐日本大使館に来ている連中を鼻で嗤うだろう。官僚というのは、かつての清朝(大清帝国)の宦官(かんがん)たちであり、中国語では太監(たいかん)という。今は中国共産党の中央書記処(しょきしょ)書記たちをいう。
太監(すなわち金タマなし男)になどならないで、宮仕えなどせずに、市井にあって悠然と生きる知識人たちの伝統と優雅さ(ただし、生活は質素で貧乏)こそは、中国宋朝の士大夫(したいふ)の道である。この対談でこのことをまさしく私は石平氏に確認し、学んだ。
石平氏は、やがて日中の真の架け橋の文人となり、日本にとっての郭沫若(かくまつじゃく、一八九二〜一九七八、政治家、文学者、詩人であり歴史家。中日友好協会名誉会長。戯曲『屈原』『李白と杜甫』などの作品がある)や廖承志(りょうしょうし、一九〇八〜八三、政治家。中日友好協会会長として日本人との知友関係が深い)の跡継ぎとなるべき重要な人物である。
最後に、私からの対談の申し出を寛い度量で快諾なさり、多くの質問に答えてくれた石平氏に叩頭(こうとう)して感謝する。石平氏は本当に頭のよい人である。この時期に、石平氏と私の対談本が世に出ることは、日本国にとって緊要な意味を持つ。
なお、この対談本が完成するまでに、先見の明のある出版人である李白社・岩崎旭社長の仲立ちがあり、湧水舎の吉野勝美氏の多大のご苦労があった。記して感謝申し上げる。
ただし、この跋文(ばつぶん)の冒頭で書いた蘭渓道隆や兀庵普寧らからの移入思想については、この本の続刊として「中国の文化・思想編」として刊行されることになった。引き続き、ご愛読いただきたい。
二〇一二年五月吉日
副島隆彦
